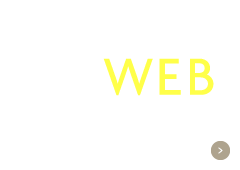嚥下障害と歯の関係

目次
はじめに
嚥下障害は、食べ物や飲み物を口から胃まで歩く過程に耐えた状態で、高齢者や脳血管疾患患者を中心に多くの方が真剣な問題です。この機能下と歯や口腔機能の関係は密接であり、適切な歯科的管理が嚥下機能の維持の重要や改善にな役割を果たしています。本記事では、下の考察から始まり、歯と嚥下機能の関係、嚥下障害に対する歯科的アプローチ、予防と改善方法について詳しく解説します。
以下のメカニズムと口腔の役割
嚥下の5期モデル
以下は複雑な神経筋協力運動であり、一般的に5つの期に分けて理解しています。 先行期では視覚や嗅覚により食べ物を認識し、摂食の準備を行います。嚼し、唾液と混合して食塊を形成します。口腔期では舌の運動により食塊を先に送り込みます。
この一連の過程において、歯と口腔機能は特に準備期と口腔期で重要な役割を果たします。 適切な咀嚼により食塊の性状態を調整し、安全で効率的な嚥下を実現するためには、健全な歯列と口腔機能が確保されます。
咀嚼機能の重要性
十分に嚼された食べ物は、表面積が増加し唾液との接触が促進されるため、嚥下しやすい性状となります。 また、咀嚼運動は唾液分泌を刺激し、食塊の潤滑性を向上させます。
せっかくな咀嚼により形成された食塊は、大きすぎたり粘性が分かれたりするため、嚥下時に喉頭や食道での通過障害を起こしやすい。これは誤嚥や嚥下困難の直接的な原因となり、栄養摂取障害や誤嚥性肺炎のリスクが高まります。
歯の欠損が嚥下機能に与える影響
咀嚼効率の低下
特に臼歯部の欠損は、食べ物を細かく砕く機能を大幅に低下させ、嚼されていない大きな食塊が形成されやすくなります。
前歯部の欠損は重要な問題です。 前歯は食べ物を噛む機能を持ち、適切なサイズに分割役割を担っています。 前歯の欠損により、大きな食べ物をそのまま奥歯で処理しようとするため、咀嚼効率が低下し、それなりな食塊が形成されます。
舌運動への影響
歯は舌の運動において重要なサポート構造としての役割を果たしています。
また、多くの歯の欠損は口腔容積の変化をもたらし、舌と歯列の位置関係を変化させます。 これにより、従来の舌運動パターンが困難になり、新たな代償となる運動パターンの獲得が必要となり、高齢者や神経疾患患者では適応が困難な場合があります。
義歯と嚥下機能の関係
義歯装着による咀嚼機能の改善
正しく製作・調整された義歯は、懐かしい咀嚼機能を大幅に改善することができます。 総義歯装着により、咀嚼効率は天然歯の約30-40%まで回復するとされており、これは嚥下機能の改善に十分な効果をもたらします。
義歯による機能回復は、強制歯の欠損部分を補うだけでなく、口腔内圧の維持、舌運動空間の適正化、顔面サポートの回復など、嚥下に関わる多くの要素を改善します。これらの総合的な効果により、安全で効率的な嚥下が実現されます。
不適合義歯による悪影響
異常、不適合な義歯は嚥下機能に悪影響を考慮する可能性があります。 義歯の動きや浮き上がりは嚼時の不安定感を引き起こし、十分な嚼を阻害します。
痛みを伴う義歯は、患者が咀嚼を気にする原因となり、結果として軟らかい食品のみの摂取に偏る傾向を生じます。これは栄養バランスの悪化だけでなく、咀嚼機能の更なる低下を目指して悪循環を形成します。
歯周病と嚥下障害の関連性
炎症による影響
歯周病による慢性炎症は、口腔内の感覚機能に影響を与え、嚥下反射の感覚を低下させる可能性があります。
重度の歯周病では歯の動き揺れが起こり、咀嚼時の痛みや不快感により十分な嚼が困難になります。これはしっかりな食塊形成の原因となり、嚥下障害のリスクが高まります。
全身への打撃効果
特に高齢者では、慢性炎症による全身状態の悪化が、嚥下機能の低下を加速させる可能性がある。
神経疾患における歯科的管理の重要性
脳血管疾患と口腔機能
脳血管疾患による嚥下障害患者に関して、口腔機能の管理は極めて重要です。麻痺側の重要な嚼筋や舌筋の機能低下により、健側のみでの嚼を軽減されることが多く、この状況では残存歯の保護と機能が維持されます。
また、麻痺により口腔ケアが困難になるため、虫歯や歯周病のリスクが生じます。これらの口腔疾患は嚥下機能の更なる見通しのため、積極的な予防と治療が必要です。
パーキンソン病と口腔機能
パーキンソン病では、口腔周囲筋の筋強剛や振戦により、嚥下に問題があります。また、薬剤の副作用による口腔乾燥も問題です。このような状況では、義歯の調整や口腔保湿などの歯科の管理が、嚥下機能の維持に重要な役割を果たします。
嚥下障害に対する歯科的アプローチ
咀嚼機能の評価と改善
残存歯の状態、咬合関係、義歯の適合状態、嚥筋の機能などを総合的に評価し、問題点を特定します。
咀嚼機能の改善には、虫歯や歯周病の治療、不適合義歯の調整や新製、噛み合わせの改善などが含まれます。これらの治療により、適切な食塊形成が可能となり、嚥下の機能の改善が期待できます。
口腔機能訓練
歯科の治療指導と並行して、口腔機能訓練も重要な治療法です。咀嚼筋の筋力訓練、舌の可動域訓練、唾液腺マッサージなどにより、口腔機能の維持・向上を図ります。これらの訓練は、歯科医師や歯科衛生士のもとで継続的に実施することが重要です。
食形態の調整
嚥下の機能に応じた食形態の調整も重要な要素です。咀嚼機能の程度に応じて、食品の固いサイズを調整し、安全で効率的な摂食を可能にします。
多方面連携の重要性
チーム医療の実践
嚥下障害の治療には、歯科医師、医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士、薬剤師など多方面が関わります。それぞれの専門性を考慮したアプローチにより、より効果的な治療が実現されます。
歯科医師は口腔機能の評価と改善を担い、言語聴覚士は嚥下機能訓練を、管理栄養士は栄養管理と食形態の調整を行います。これらの専門職が密接に連携することで、患者個人の状態に応じた最適な治療プランを提供できます。
継続的なモニタリング
定期的な歯科入学により口腔機能の変化を評価し、必要に応じて継続して治療計画の修正を行います。また、在宅やでの口腔ケア状況の把握と指導も重要な要素です。
予防的アプローチ
初期からの口腔機能管理
嚥下障害的な予防には、早期からの口腔機能管理が重要です。 定期歯科検診により口腔疾患の早期発見・治療を行い、咀嚼機能の維持に努めます。 また、加齢に伴う口腔機能の変化を早期に観察し、適切な対応を行うことが重要です。
生活習慣の改善
喫煙や過度の飲酒は歯周病のリスクを高め、間接的に下機能に悪影響を与えます。これらの生活習慣の改善は、口腔の健康の維持とともに嚥下機能の保護にも重要です。
また、バランスの取れた食事と適度な嚼により、口腔機能の維持・向上を取り組むことができます。硬いめの食品を意識的に摂取することで、咀嚼筋の筋力維持にも効果があります。
まとめ
歯の欠損や口腔疾患は嚥下機能を低下させ、確実な食塊形成により嚥下障害を起こします。
多目的連携による包括的なアプローチと継続的なモニタリングにより、患者個人の状態に応じた最適な治療を提供することが重要です。
歯科医療従事者、医療・介護関係者、そして患者・家族が嚥下障害と歯の関係について正しい考え方持ち、正しい対応を行うことで、安全で豊かな食生活の実現が可能となります。
患者様に寄り添い、丁寧で優しいケアを大切にする、怖くない、痛くない歯科医院です。
泉南市市おすすめ、泉南市ほほえみ歯科りんくう院、是非、ご来院ください。